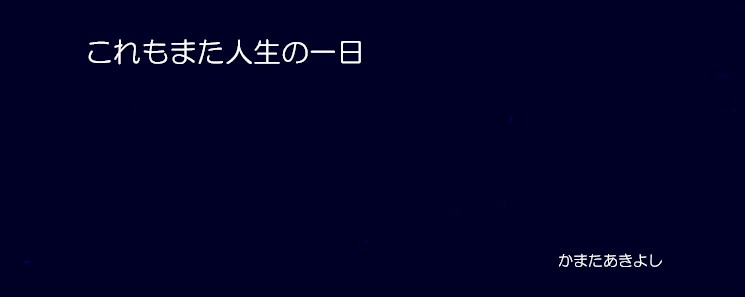ノストラダムスを話題にする度に、この詩について語れと言われる。もう10年くらいはこの詩に対する自分の考え方は大きく変化していない。
この詩について自分が語ると、それはかなり投げやりというか、みんなの期待には沿えないと思うので、まず一般的に受け入れられている訳と解釈を述べてからのほうがよいだろう。
L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra vn grand Roy d'effrayeur:
Resusciter le grand Roy d'Angolmois,
Auant apres Mars regner par bon-heur.
年は一九九九年と七ヶ月
恐怖の大王が天より姿を現わすだろう
彼はアンゴルモアの大王を蘇生させ
その前後は火星が幸せに支配する
(山根和郎 訳)
これが今インターネットで見ることができる(訳者名の明らかな)一般的な訳。
これがP・ブランダムールの本では
一九九九年七つの月、
恐怖の大王が空より来たらん、
アンゴルモアの大王を蘇らせん、
マルスの前後に幸運で統べんため。
(高田勇・伊藤進 訳)
となっている。あまり大きな違いはないようだが、高田・伊藤訳は三行目四行目を
二行目の「恐怖の大王」が降臨する理由として捉え、倒置と見なした訳にしているのに対し、山根訳は三行目以下を「恐怖の大王」の登場以降を順序だてて訳してある。
どちらが正しいということではないが、山根訳には「・・・であろう」とか「彼は」という、原詩では使われてない単語が(この詩だけにかぎらず多数)出てくることから、これが他の言語(多分英語だろう)に訳されたものを日本語に訳した「重訳」であるということがわかる。これではノストラダムスの日本語訳としては「参考」レベルのものでしかないということは言っておかなければならない。
単語をひとつひとつ検証してゆくと、
まず一行目のnonanteという言葉にまず引っ掛かる。これは「90」という数を表す南仏あたりの方言。ベルギー(フラマン語)でもこのnonanteは使うが、16世紀当時とはいえこのnonanteという言葉の使い方、第一行目の登場は何か唐突な感じは否めない。デカラシッブという十音節法のためだけに無理矢理あてはめた感じがする。特に深い意味はないであろう。
二行目のd'effrayeurはだいたい「恐怖の~」と訳されるが、それが仮にeffrayerの異形だとしても、「世の終わりの到来級の恐怖」というニュアンスはない。国家間の紛争といった規模の恐怖か。(友人が、ニコの古いラテン語辞典を必死に繰ってもその程度だったと言っていた。)「空から降臨する恐怖の大王」というのは占星術的な表現で、彗星が見えるとか日食であるとかの天変地異の先駆けとされる現象を目にする事ができるという表現であろうと言われている。「言われている」というのは、ノストラダムスの他の預言詩に頻繁に登場しているからだが。だとすれば、「王の交代」であるとか「急激な政変」であって、決して「世の終わり」とは読めないのがこの詩なのである。ノストラダムスがもっとどぎつい表現で大量虐殺を表現した詩ならほかにいくつかある。
三行目、Angolmoisはいまさらながらだが、アングームという地名と、その地の領主から国王にまで上り詰めたフランソア一世を指すのではないかと思われる。決してモンゴリアのアナグラムでもなければアンコロモチでもない。
フランソワ一世について少し長い説明をする。言ってしまえば「フランス」という国の中興の祖ともいうべき国王であるが、当時まだローマや他の列強国に挟まれ、軍事的にも文化的にも立ち遅れていたフランス国内を再統一している。彼は芸術にも関心が深く、その最大の功績は、当時イタリアで不遇をかこっていたレオナルド・ダヴィンチを受け入れたことだといわれている。王は、ダヴィンチを厚遇をもって招き、城の近くにあった母のための立派な城屋敷をダヴィンチに充てて、ダヴィンチと親交を深めたのだ。
フランソワ一世は、かつて意外な形で日本でも広く知られるようになったことがある。ダヴィンチは数少ない自作品を一緒にフランスに持ってきたのだが、その一枚が「モナリザ」であったのだ。ま、これが今ルーブル美術館に「モナリザ」が所蔵されている最大の理由である。イタリア側からは散々「モナリザを返せ」と言われながらも「ダヴィンチを追い出したくせに今更なにを言う」とフランス側が応酬するという長閑な論戦が300年も続いていたりするわけだが。さて、その「モナリザ」の絵がかつて日本に来たことがあった。1975年のことだったと記憶しているが、実はそのとき一緒に展示されていたのがなにを隠そうダヴィンチの手によらない「フランソワ一世」の肖像画であったのだ。また、最近では「ダヴィンチ・コード」でこのフランソワ一世の名前を耳にした方もいるかと思う。
で、話をノストラダムスの詩に戻すが
四行目のAuant apresは「その前後・・・」だが、時間的な前後ととれるし、地理的な意味での「前と後ろ」ともとれることは付記すべきであろう。版によって「,(アポストロフィー)」があったりなかったりで、それがマルスに掛かるのか、アンゴルモア王にかかるのか、恐怖の大王にかかるのかはすぐには判断しにくいが、遂語訳だとどうしてもマルス(火星=戦争、軍神)に掛かるように訳してあるようだ。
「戦争前と戦争後(軍神登場前と登場後)」、「マルス(軍神)と立ち向かえば恐怖だが、その配下につけば幸福である」と解釈できるし、交錯韻を踏まえて解釈すれば「恐怖の王=アンゴルモア王=マルス」で、つまり「軍隊を前にすれば恐怖であるが(敵にとっては恐怖の大王であり)、盾にして後ろにいれば(フランソワ一世の時代のように)幸福である」ということを言っているのだと思う。
これらを踏まえて、上記の二つの訳を読んでもらえばこの詩に関する考察の90%は出来たも同然ではないかと思われる。
この詩は、フランソワ一世のような優れた王が、恐怖の大王といわれるような天の兆し(日食といわれている)とともにフランスに再来するむことを(預言として)描写したのであろう。この再来したアングームの王は、周囲の国々にとっては(軍事力を盾に)脅威となるが、国内においては「幸福な時間」と呼ばれる、ということであろう。
まあ、これが(まともな)研究者による一般的な解釈である。私もそれでいいのではないかと思う。
で、これから以下述べるのは私の個人的な見解と解釈であり仮説なのだが
そもそもこの詩の収められている第十巻というのは、第八巻以降がすべてそうであるようにノストラダムスの死後、息子のセザールの手によって出版された、言ってしまえば遺稿集、未発表詩集みたいなものだ。それが出版されることがはたしてノストラダムスの意思に沿ったことなのかどうかをまず考える必要があると思われる。
特に第十巻はまるでとり急いだようにきっちり百編揃っており、遺稿の残され方としては極めて不自然としか言わざろう得ない。たとえなにかの事情があったにせよ、ノストラダムスの中で、この第十巻はとりたてて重要ではなかったのではないかと思われる。もし仮にあなたがノストラダムスだとして、自分が一番伝えたい重要な詩を、果たしてこんな位置に置くだろうかを考えてみればわかるであろう。
自分自身この第十巻を最初に通して読んだときは、詩としての奥深さがほとんど感じられず、果たしてこれは同一人物の手によるものなのだろうかと悩んだくらいだ。技法的にいえば、交錯韻を考慮して理解しようとしてもどうなるようなものはほとんとなく、どちらかといえば「単なるダジャレじゃん!」といいたくなるような程度の低い脚韻でとどめた詩が多いのである。
で、私はこの詩を、第三者の手による、ノストラダムスの手法を真似た贋作であると位置付けている。おそらく犯人はノストラダムスの息子セザールか弟子達ではないか。たとえそうでなくともせいぜいノストラダムス自身の「下書き」、あるいは「習作」程度のものであったろう。
という観点から私はこの詩を(ノストラダムスの詩として)訳したり、考察したりはしないのである。
1996年か1997年のことだと思うが、私は渋谷だか新宿のとある場所で「インターネットにおける都市伝説」というライブイベントに招かれて、講師としてこのような事を約100人の聴衆の前で喋ったことがあったのだ。
会場はどっちらけであった。喋ってる最中に「ツマンネ~」とか「ワカンネ~」という声があちこちから聞こえてきたくらいだ。あれは失敗だったな。なにせ会場にお集まりいただいた聴衆のほとんどががギャルの皆さんだったし。
自分以外は、稲川淳二ばりの怪談とかUFOとかの話で大盛り上がりであった。
自分もダジャレやこじ付けで恐怖を煽るような珍解釈を披露したほうが、このイベントに水を差すようなことはしなかったろう。しかし、なんであんなイベントに呼ばれたんだろう。そっちのほうが謎だわい。
(初出『人生の一日<旧バージョン>』05.06.12)
参考及び引用
HP『ノストラダムスサロン』
HP『ノストラダムス研究室』
『ノストラダムス予言集』岩波書店 P・ブランダムール著 高田宏・伊藤進共訳
『トンデモノストラダムス大予言』『トンデモ予言の後始末』ともに大田出版 山本弘著
その後2ちゃんねる過去ログ「ノストラダムスの今後の展開が・・・(1と2)」を参考に手直して05.06.20ごろに修正バージョンをアップしてます。